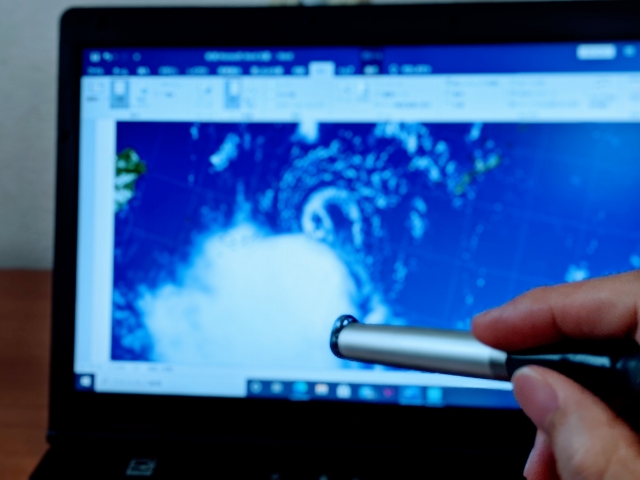台風の名前は誰が決めている?国際ルールと仕組み
ニュースで耳にする「台風○○」。実はこの名前、日本だけで決めているわけではありません。台風の名前は、アジアや太平洋地域の国々が集まる「台風委員会」という国際機関で管理されています。
この委員会には日本をはじめ、中国、韓国、フィリピン、アメリカなど14の国と地域が参加。それぞれがあらかじめ提案した名前をリスト化し、順番に使っていく仕組みです。名前を付けることで情報が共有しやすくなり、防災意識の向上にもつながります。
命名リスト「140個」の正体と使い回しルール
台風の名前は、加盟国が提案した140個の名前リストから順番に使われます。動植物や星座、伝説など、由来はさまざま。たとえば日本からは「カジキ(魚)」「テンビン(星座)」「フンシェン(風神)」などが提案されています。
リストは一周するとまた最初に戻るため、同じ名前が数年おきに再登場することもあります。混乱を防ぐため、発音や意味に問題がある名前は見直されることもあります。
意外と面白い!各国が提案したユニークな台風名
国によって命名の傾向や背景には、それぞれの文化や歴史が色濃く反映されています。韓国は「チャンミー(バラ)」のように花の名前を多く採用し、優美で柔らかな印象を持たせます。中国は「ムジゲ(虹)」など自然現象にちなんだ美しい響きの名前が多く、自然崇拝や景観美を大切にする文化が感じられます。フィリピンは神話や伝説にちなんだ名前を好み、「ラカン(神話の王)」や「アモル(愛)」など、物語性のある名前が並びます。
こうした名前は単なる識別記号ではなく、その国の気候風土や価値観、人々が大切にしてきた象徴を映し出す鏡のような存在です。由来を知ることで、台風名からその国の暮らしや歴史を垣間見ることができ、ニュースを聞く視点も広がります。
二度と使われない台風名「引退制度」とは
大きな被害をもたらした台風の名前は、「引退」して二度と使われません。過去には2013年の「ハイエン」や2022年の「ナンマドル」などが引退しました。これは被災者への配慮と、同じ名前による混乱や心理的負担を避けるための制度です。引退が決まると、その国が新しい名前を提案し、命名リストに加わります。新しい名前もまた文化や由来を持ち、次の世代へ受け継がれていきます。
台風名と強さは関係ある?正しい見方と注意点
「かわいい名前だから弱そう」「強そうな名前だから危険」…そんな思い込みは誤解を招きます。台風の勢力や進路は名前ではなく、気象庁や市町村の公式発表で確認することが大切です。名前はあくまで識別のためのラベルに過ぎません。油断せず、最新の正確な情報をしっかりチェックし、安全な行動に役立てましょう。
海外の台風・ハリケーン命名ルールとの違い
アメリカでは男女の名前を交互に使い、アルファベット順に並べるユニークな方法を採用しています。一方、フィリピンは国際名とは別に、自国用の名前も並行して使用する「二重命名」制度を導入。これにより住民が親しみやすく、迅速に情報を受け取れるよう工夫されています。国や地域ごとにこうした違いがあり、文化や言語の個性が命名にも反映されています。
台風の名前の未来予測|AIや市民参加型の可能性
これからはAIが命名に関わる時代が来るかもしれません。検索のしやすさやSNSでの拡散性を考慮した、短く覚えやすい名前が選ばれる可能性があります。また、一部の国では一般市民が名前を提案できる制度も始まっており、より多くの人が命名に参加する動きが広がっています。こうした取り組みは、防災意識や地域文化の共有にもつながっていくでしょう。
まとめ|台風名を知ることでニュースがもっとわかりやすくなる
台風の名前には、国際協力や文化、歴史が詰まっています。その意味や背景を知ることで、ニュースを聞く目線が豊かになり、防災意識も自然と高まります。次に台風名を耳にしたら、その背後にあるストーリーにも思いを馳せてみてください。
“`